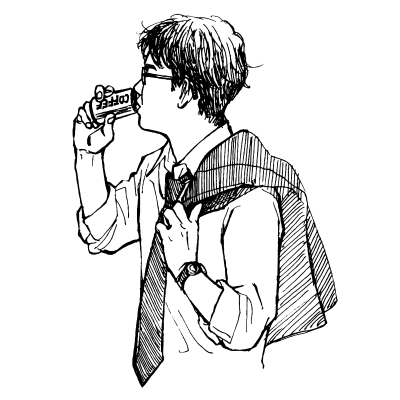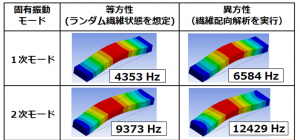エンジニアは設計するだけが仕事ではなく、社内でプレゼンテーションをする機会が多い職種の1つです。それは会社の商品をどのような形で誰に向けて開発を進めるのかを社内的に承認を得て進める必要があるからです。逆に言えば、設計はできるが、人前でプレゼンすることが苦手というエンジニアは1人前とは言えないでしょう。それだけプレゼンの能力はエンジニアにとって必須であると言えます。なぜなら答えの見えないもの(未来の自社製品)に対して相手に共感を得られなければならないからです。今回は、そのプレゼン資料の作成に関して、特に説得力のあるプレゼン資料の作り方について解説していきます。
保護中: 商品開発のためのプレゼン資料の作り方!現役エンジニアが語る資料作成7つのステップ